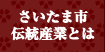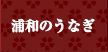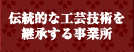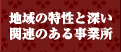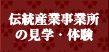トップページ
>
伝統産業最新情報
伝統産業最新情報
-
2023年1月10日
昭和57年の創業。人形工房ブランド『ひととえ』では、雛人形、五月人形の製造卸、販売をしています。今までのようにその季節だけに飾るだけではなく、現代の住宅の中でインテリアとして違和感なく溶け込み、いつでも、そしていつまでも飾れるよう創意工夫が施された人形が数多く揃います。衣裳には上質な絹織物を、胴柄にも昔ながらの桐塑(とうそ)を使用するなど、ひとつひとつ、熟練した職人さん達の手によって製作されていま […]
-
2023年1月10日
昭和46年設立の江戸木目込専門の製造卸と小売りの店。節句人形工芸士の初代重治から、現在は2代目ゆうきが中心となって製作。店内は、女性ならではの感性をいかした独自の作風の節句人形が並び、毎年新作を発表しています。展示会に遠方から足を運ぶ人が増えたりと、少しずつ認知されてきたことを実感しているとのこと。作品のモチーフに源氏物語や風水を起用したりと、斬新なデザインは2代目ゆうきの特徴となっています。 【 […]
-
2023年1月10日
昭和60年創業。雛人形は工房ひな雛、五月人形は工房真のブランド名にて、江戸木目込人形の技法で製作した木目込み人形を販売。五月人形については、オリジナルの各種兜や鎧飾りも好評。従来からの伝統的な製法と高い品質にこだわりながらも、コンパクトなサイズを中心とした現代的な住宅にも飾りやすい品を提案しています。 【所在地】見沼区大字蓮沼491-1 【電 話】048-680-5631 https://kobo […]
-
2023年1月10日
1月6日の埼玉新聞11面に、小山本家酒造さんが、女性の感性を生かして純米酒を開発したことが掲載されました。
-
2022年11月17日
岩槻の人形博物館にて人形作りや人形文化を体験するワークショップ「にんラボ特別編」が開催され、埼玉新聞に掲載されました。